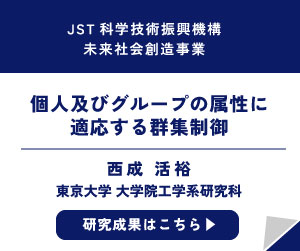傾斜地・盛り土・擁壁の安全性に注意
宅地開発により、各地で丘陵が崩されたり、谷が埋められたりして地形が人為的に改変されている。この結果、住む場所として安全なのか疑問符の付く地域も多く生じている。
急傾斜地もその一つである。急傾斜地とは30度以上の傾きのある土地で、崩落すればその上や下に住む住人は大きな被害を受けることになる。1976年の呉豪雨災害を契機に国は急傾斜地法を制定し、自治体では急傾斜地を指定し対策工事を行っているが、地価が下がる、負担金が払えないなどの理由で工事に住民の同意が得られないこともあった。現在では負担金についても自治体が負担するなどして軽減が図られ対策が進んできている。
盛り土も安全面から問題である。2004年新潟中越地震では、盛り土の崩落により大きな被害が生じている。長岡市の高町団地は、1970年代後半に魚沼丘陵の尾根部を削り、切土・盛り土によって平坦に造成したもので、この盛り土部分が地震により崩落し、その上に建っていた住宅が崩壊するなどの被害を受けた。造成にあたって法基準を満たしていても、大地震では崩落する危険性があるといえる。
擁壁も問題がある。擁壁はその所有者が適切に管理しなければならないが、老朽化に伴う維持には多額の経費が掛かることから危険であっても放置されがちである。2021年6月に大阪市の西成区で起きた空石積みの擁壁の崩壊や、2025年9月に起きた東京杉並区の擁壁崩壊もそうした例である。西成区の擁壁は、長年の雨水の浸透により石積みの裏込め土が流出して空洞になり擁壁上部が座屈したことで崩落し、その上に建っていた2棟の連棟住宅が崩壊したものである。また杉並区の擁壁は老朽化により亀裂が生じ40年以上区から指導されていたが放置され、ようやく対策工事に入る矢先に崩壊したものである。この擁壁はかさ上げされたために、その盛り土による影響もあったと指摘されている。50年以上経過し老朽化した擁壁は、全国で200万か所以上存在するといわれている。
こうした崖地などは、先人が住まなかった場所が多い。現在住めるようになったのは、土木技術の進歩があったからだともいえるが、管理がおろそかになっていては安全上問題である。擁壁の建設に関する法整備は進んできたが、管理については所有者任せにして長年法整備等の対策を講じてこなかったことも事故の根底にあるといえる。今後、法整備が必要だろう。 しかし法整備が進んだとしても、所有者の責任は無くならない。そのリスクの有無を確認するため重要なことは、住んでいる場所や住もうとしている場所について知ることである。その際、古い地名も土地の成り立ちを調べる大きなヒントになる。土砂災害が発生した土地には、蛇崩、蛇抜のように蛇や猿、柿、倉などが使われている。災害から身を守るには、土地の歴史や先人の教えを忘れてはならない。